先日、近所のスーパーで思わぬ出会いがあった。 お肉コーナーに並んだ、きらびやかな「A5ランク牛肉 半額」の文字。普段は手が出ない高級品だけど、半額なら話は別。ちょっとした冒険心が湧いてきて、思い切って買ってみることにした。
家に帰って、塩だけでシンプルに味付けしてフライパンで焼いてみた。ジュウ…という音とともに立ちのぼる香り。ひと口食べた瞬間、思わず「うまっ」と声が漏れた。とろけるような食感、濃厚なのにしつこくない脂。テレビで「A5は別格」と言われていた意味が、ようやく実感として腑に落ちた。
でもふと、「A5って、そもそも何がすごいの?」という疑問が湧いてきた。なんとなく「A」が高級、「5」が最高、というイメージで受け止めていたけれど、実際のところはどうなのだろう?
「A」と「5」の意味、実は全然違う
調べてみると、牛肉の格付けは「歩留等級」と「肉質等級」の2つの指標で決まっているらしい。
まず「A・B・C」は歩留等級。これは牛一頭からどれだけ商品になるお肉が取れるかの割合を示すもの。
- A:たくさん取れる
- B:標準的
- C:少なめ
つまり「A」は量の話。美味しさとは直接関係ない。
一方、「1~5」の数字は肉質等級。こちらは霜降りの度合いや肉の色、脂の質など、味や食感に関わる部分を評価したもの。
- 5:最高ランクの肉質
- 1:最低ランクの肉質
つまり、消費者目線で重要なのは「5」の方。味や食感を左右するのはこの数字なのだ。
B5やC5も存在する?でも見かけない理由
ここでさらに気になるのが、「じゃあB5やC5ってどうなの?」という疑問。肉質が「5」なら、AでもBでもCでも美味しいはず。なのに、スーパーではほとんど見かけない。
その理由は主に3つある。
1つ目は、黒毛和牛の多くが歩留まりの良いAランクになるため、そもそもBやCになることが少ないということ。 2つ目は、C5は理論上存在するけれど、実際にはほとんど見かけない幻のランクであること。 3つ目は、流通の段階でAランクが優先されるため、BやCは市場に出にくいということ。
つまり、味は同じでも、流通や表示の仕組みの中で「A5」が圧倒的に目立つようになっているのだ。
「A5=美味しい」はちょっとした誤解かも?
今回の体験を通して、「A5だから美味しい」と思っていたのは、ちょっとした勘違いだったことに気づいた。 実際には「5」が美味しさの指標で、「A」は量の話。だから、もしB5やC5が店頭に並んでいたら、それも同じくらい美味しい可能性がある。
とはいえ、現実にはA5が主流。だからこそ、見かけたら「これは肉質最高ランクなんだな」と安心して手に取れるのも事実。今回のように半額で出会えたら、それはもう運命の出会いと言ってもいいかもしれない。
お肉選びがちょっと楽しくなる
格付けの仕組みを知ると、スーパーでのお肉選びがちょっとした冒険になる。 「A5」だけじゃなく、「4」や「3」も気になってくるし、もし「B5」なんて表示を見かけたら、それはレアものかもしれない。出会えたらA5のお肉と食べ比べをしてみたい。レアものだからB5のお肉の方が高価だったりしてね。
次にお肉コーナーを歩くときは、ラベルの数字にちょっとだけ注目してみてほしい。 超レアC5ランクお肉が並んでいるかもしてないですよ!

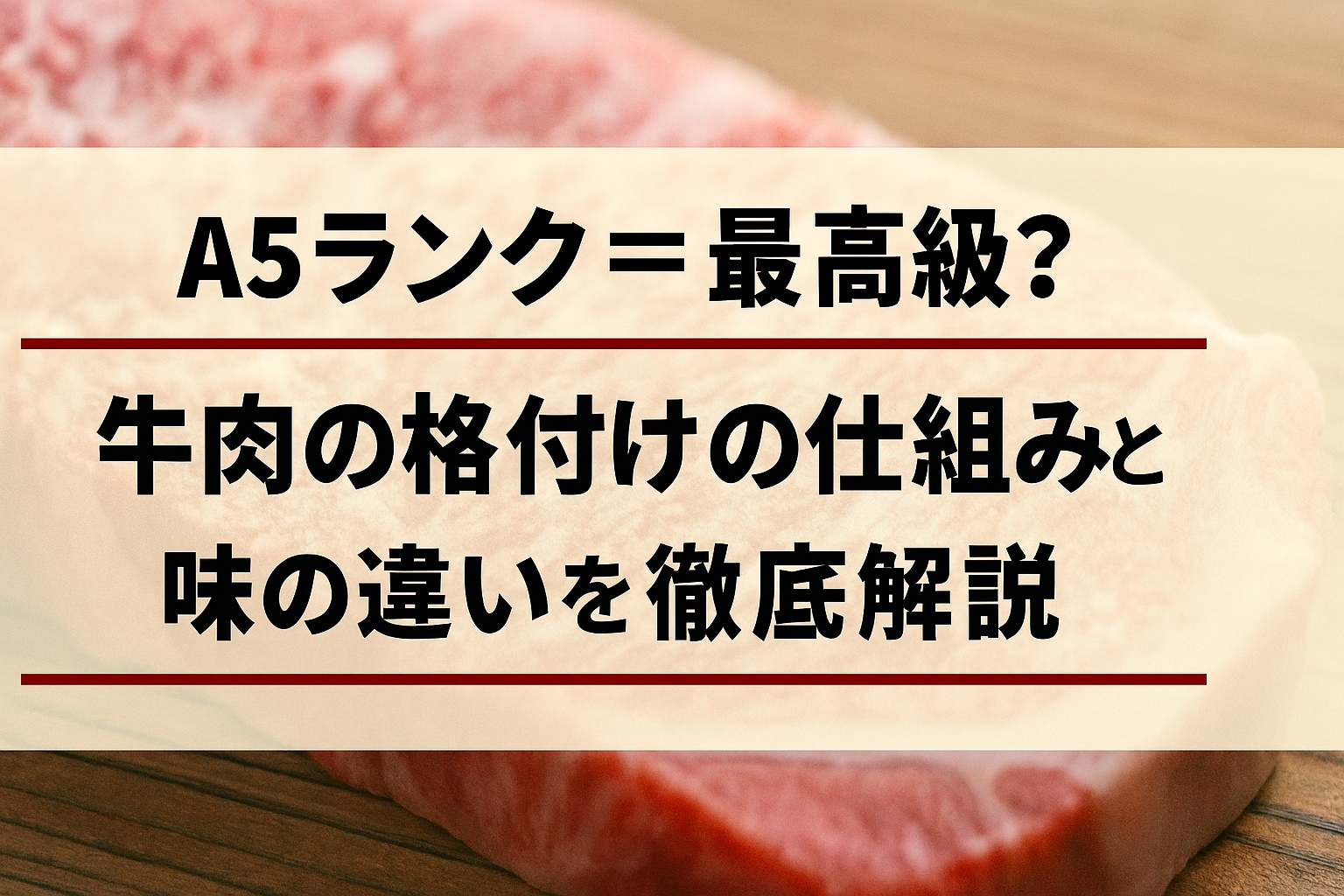
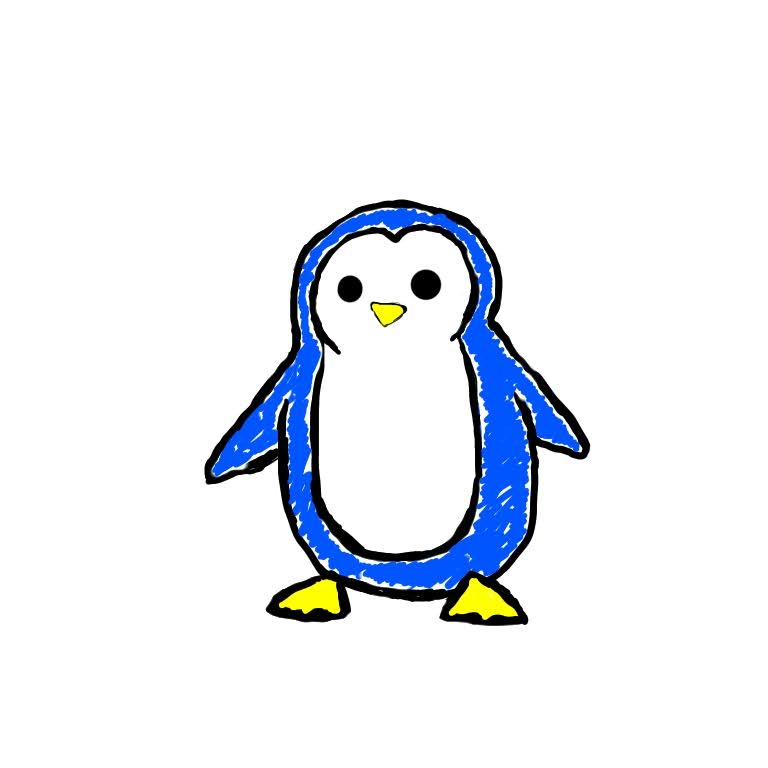




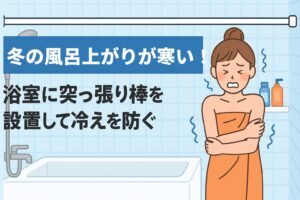

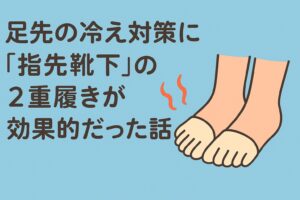
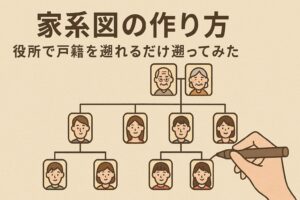
コメント