会社員として働いていると、ある日突然「異動」や「転勤」の辞令が届くことがあります。 その理由を聞いても、「人材育成のため」「組織の活性化」「業務上の必要性」など、どこか抽象的で納得しづらいことも。
この記事では、企業が語る“建前”と、実際に動いている“本音”を整理しながら、異動の裏にある人事の力学を読み解いていきます。
人事が語る「建前」の異動理由
企業が公式に説明する異動・転勤の理由は、以下のようなものが一般的です。
- 人材育成・キャリア形成 → 多様な経験を積ませるためのジョブローテーション
- 組織の活性化 → 長期在籍によるマンネリ化を防ぎ、新しい視点を取り入れる
- 業務上の必要性 → 新規事業の立ち上げ、人員不足の部署への補充
- 昇進条件の達成 → 管理職候補として、複数部署での経験が必要
これらは就業規則や人事制度に沿った、いわば“模範的な理由”です。
実際によくある「本音」の異動理由
現場では、もっと人間くさい理由で異動が決まることもあります。たいていの場合の異動は部門のトップの関与があるもの。部門の運営を良くするためには人員整理が近道だもの。
1. 協調性のない人・トラブルの火種を外す
- チーム内で摩擦を起こしている人を“空気を変える”目的で異動。人間関係のトラブルが無くて風通しが良い職場って働きやすいですよね。
2. 仲が良すぎる2人を引き離す
- 極端に仲が良い関係が業務に支障をきたす場合、あえて分断。一部の人だけ働きやすいというのは他の人には働きにくいということも。部門全体の運営の不和のもとは断つべし。
3. 仕事の出来が悪い人を整理
- 部門の運営責任者としては部門の業績アップにつながらない人は排除したいよね。目立たない部署や負荷の少ない業務へ静かに配置転換。
4. 失敗に対する“処分”としての異動
- プロジェクトのミスや信頼喪失の“後処理”としての異動。嫌がらせの罰ゲーム。
5. 上役による“引き抜き”
- 強い権限を持つ上司が、お気に入りの部下を別部署へ連れていく。自分の成績アップのためには「言うことをよく聞く」「仕事のできる」部下を並べたいもの。
6. いなくなっても困らない人を外す
- 人を置いておくだけで人件費はかかる。人件費カットは手っ取り早いコストカット。この部門に君は要らないから他の所で役に立ってね。
7. 辞められない人をハズレ部門へ
- 仕事内容がキツくてどんどん人が辞めていくハズレ部門ってありますよね。そういうハズレ部門に「家族が増えた」、「住宅ローンを組んだ」などの事情で仕事を辞めにくい状況の人を送り込む。きつい職場だけど辞めずに頑張ってね。
異動は「評価」ではなく「調整」
異動は必ずしも昇進や降格を意味するものではなく、組織のバランスを保つための調整手段でもあります。 ただし、本人にとっては納得できないケースも多く、説明不足や配慮の欠如が不信感につながることも。だいたいの場合は個人の事情より会社の都合が優先される。会社の言うことは聞かないといけないのが現実。逆らっても良いことないよね。
希望を通すには「会社目線」で語る
異動を拒否したり、個人の事情だけを押し出すと「協調性がない」と見なされるリスクも。 希望を通したいなら、「会社のために何ができるか」を軸に伝えるのが効果的です。
伝え方の例
❌「家庭の事情で転勤は避けたいです」 ✅「現在のスキルを活かして、○○部門で業務効率化に貢献できると思います」
❌「今の部署が合わないので異動したいです」 ✅「○○部門では、これまでの経験を活かして即戦力として動けます」
まとめ
異動・転勤の理由には、建前と本音の両方がある。 そのギャップを理解することで、納得感のあるキャリア選択ができるようになる。 希望を通すには、「会社の都合を理解したうえで、自分がどう貢献できるか」を言語化する力が鍵。

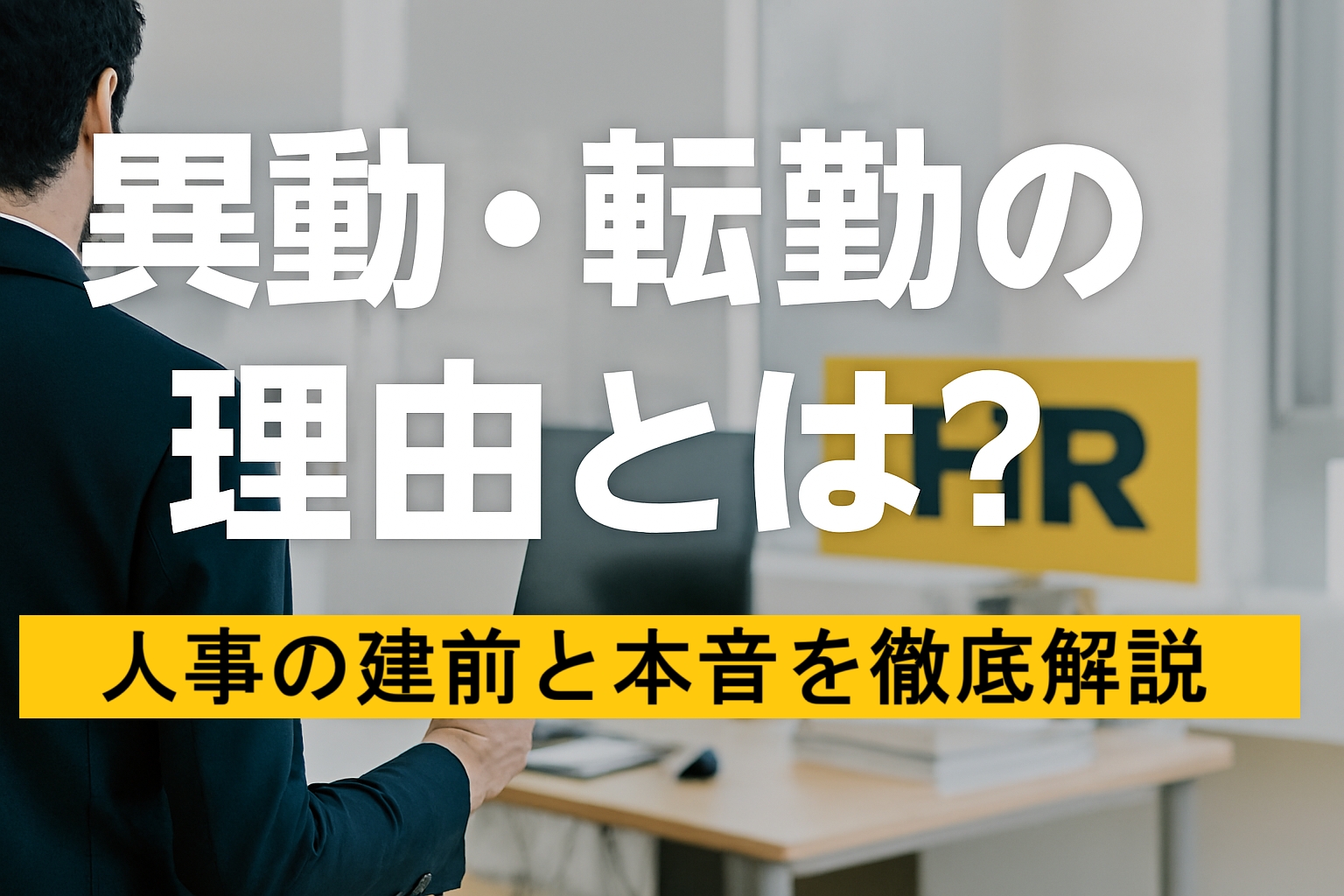
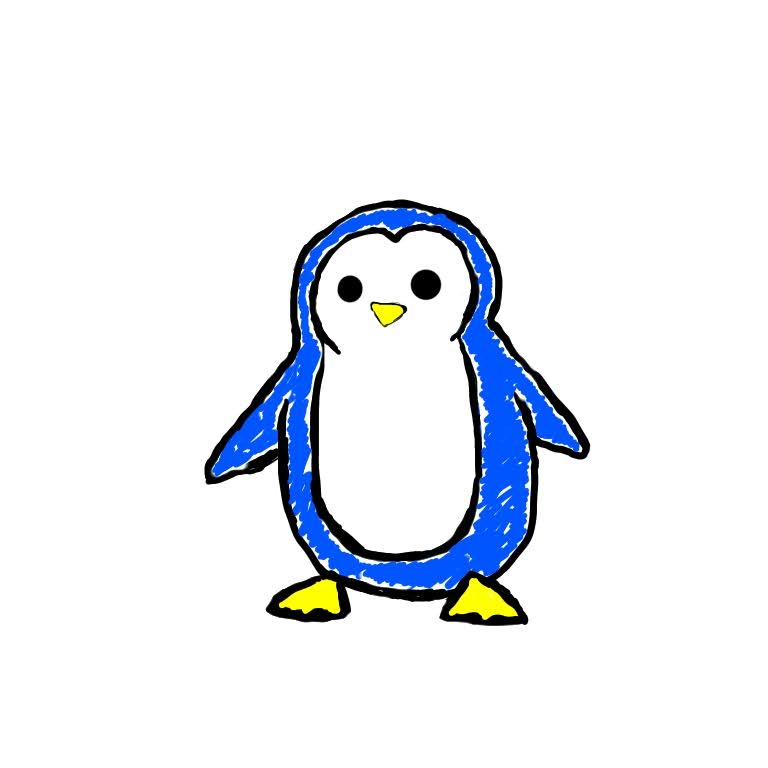




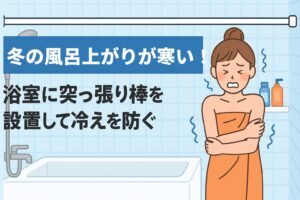

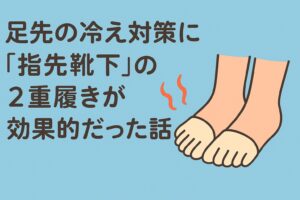
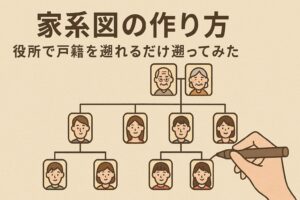
コメント