「春は3月から?」 「9月はもう秋?」
当たり前のように使っている「春夏秋冬」という言葉ですが、実はその定義は一つではありません。暦の上、気象、そして私たちの社会生活、それぞれの観点から季節の捉え方が変わってきます。
今回は、それぞれの「春夏秋冬」の定義と、私たちがなぜ季節にズレを感じるのかを解説します。
1. 気象庁が定めた「春夏秋冬」
天気予報などで最も一般的に使われるのが、この区分です。
- 春:3月・4月・5月
- 夏:6月・7月・8月
- 秋:9月・10月・11月
- 冬:12月・1月・2月
この定義は非常にシンプルで分かりやすい反面、実際の気温や体感とは異なることもあります。「3月なのにまだ寒い」「9月なのに真夏日」といったギャップを感じやすいのは、この気象庁の区分と実際の気候がずれているためです。
2. 「暦の上では」の「春夏秋冬」
ニュースなどで「暦の上では春ですが…」という言葉を聞いたことはありませんか?これは、日本の旧暦や二十四節気に基づいた考え方です。
- 春:立春(2月4日頃)〜
- 夏:立夏(5月6日頃)〜
- 秋:立秋(8月8日頃)〜
- 冬:立冬(11月8日頃)〜
この区分では、春は2月上旬から始まります。体感としてはまだ真冬ですが、昔の人々はこうした暦を使って季節の移り変わりを感じていました。
3. 社会的な「春夏秋冬」
私たちの生活に深く根付いているのが、新年度・新学期を基準にした季節感です。
- 春:4月
- 新年度や新学期が始まり、生活が大きく変わるスタートの季節。
- 夏:7月・8月
- 本格的な暑さや、夏休み・お盆休みなど、長期休暇のイメージ。
- 秋:9月・10月
- 新学期や下半期の始まり。過ごしやすい気候で、行楽や食事が楽しい時期。
- 冬:12月・1月・2月
- 年末年始のイベントや、本格的な寒さを感じる時期。
この区分は、私たちの社会的な活動や行事と結びついているため、最も身近な「季節」かもしれません。
4. 企業が使う「春夏秋冬」
製品の発売日などに使われる「今冬発売」や「今夏発売」といった表現も、上記とは異なる独自の期間を指すことがあります。
例えば「今冬発売」の場合、単に12月〜2月だけでなく、年度末の決算期に合わせて3月上旬までを指すケースも少なくありません。これは、企業のマーケティングや販売戦略が大きく影響しています。また、発売日をあいまいにして、「もしものスケジュール遅れに対して保険をかける」という意図もあるかもしれません。
まとめ:あなたはどの季節感?
同じ「春夏秋冬」でも、その定義は一つではありません。
- 天気予報なら気象庁の区分
- 「暦の上では」なら二十四節気
- 新生活のイメージなら社会的な季節感
もし「3月は冬?春?」と聞かれたら、どの観点から答えるかで正解が変わってきます。うっかり「春になったら会おうね!」なんて約束をしてしまった場合にはお互いの認識に1か月以上のズレなんてことも(笑)
あなたの「春夏秋冬」は、どれに一番近いですか?

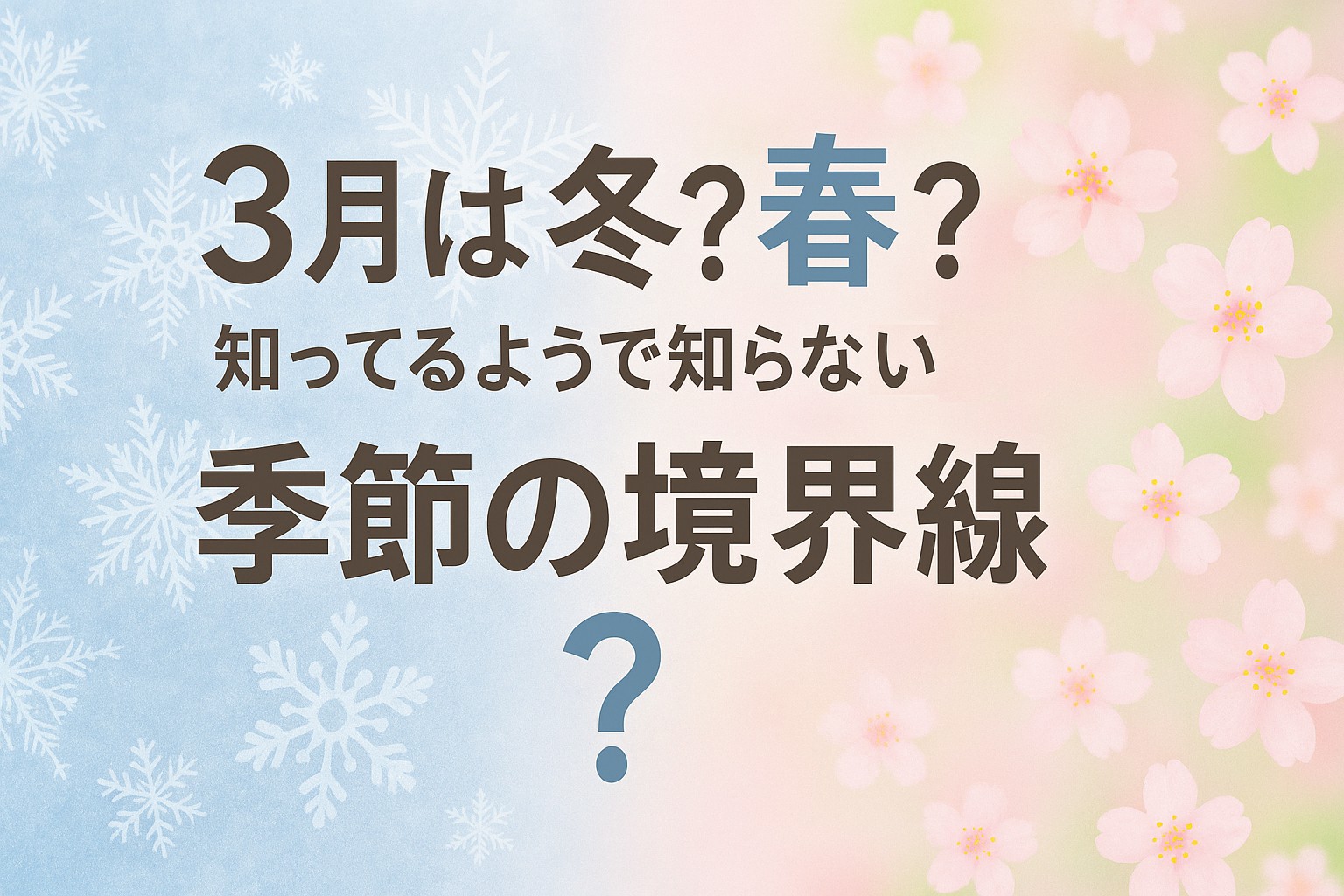
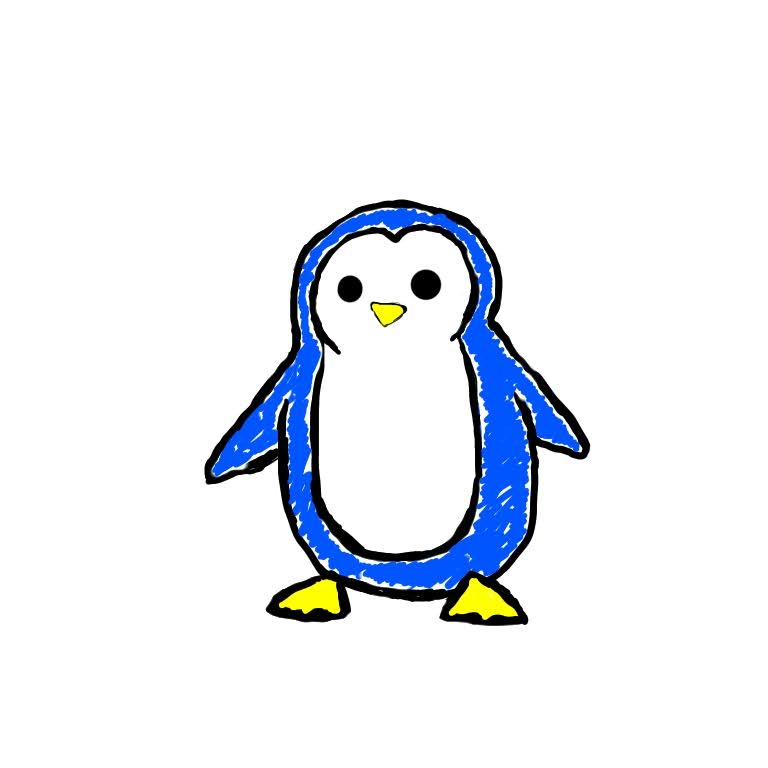

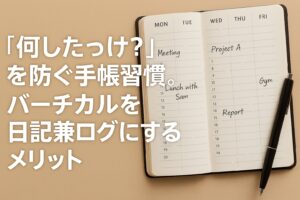


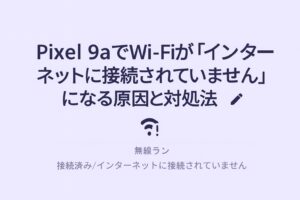
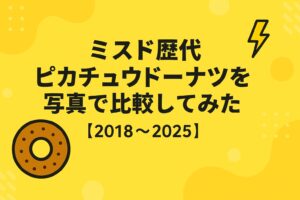
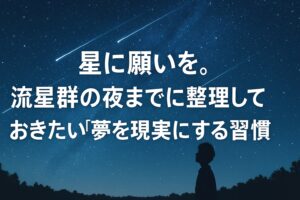

コメント